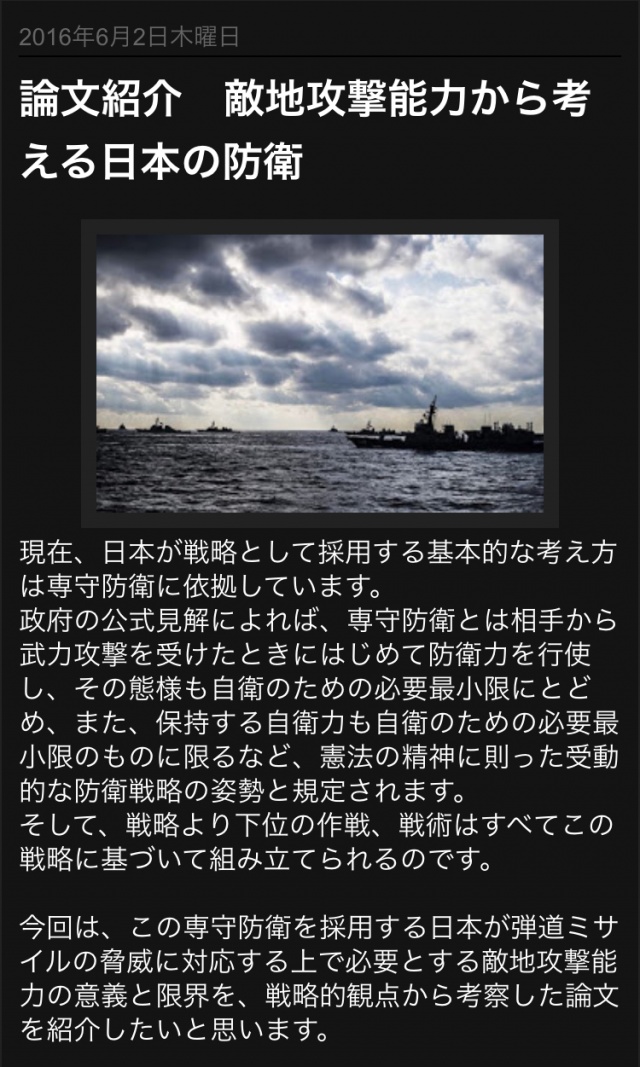ここ最近、いずも空母化や空中発射型巡航ミサイルなど、いわゆる敵地攻撃能力の議論が活発化してますが、まだ本質的な議論になっていないのも皆さん何となく感じておられるかと思います。
左派に多いですが、防衛とは何もせず侵攻されたら元の場所まで押し返すもの...などと勘違いされています。しかし、フラー少将(機甲戦で有名な)は、戦闘の勝利は、攻撃と防御を組み合わせて得られるもの、敵軍粉砕の場合は攻撃転移しなければならないと言っており、孫子の兵法でも「勝つべからざる者は守ればなり。勝つべき者は攻むればなり...」(あくまで孫子は勝てる見込みがあるなら攻撃転移しろと言っているだけです)と記されていて、攻勢防御という軍事戦略があります。またフラー少将は続けて限定攻撃があってこそ、防衛が成り立つとも言っておられます。チャンネルくららでお馴染みの織田元空将も拒否的抑止に敵地攻撃能力は矛盾しないと言及されてますよね。この論文紹介でも政府解釈では、鳩山一郎首相が一定の制約下攻撃を加えることを自衛の範囲と述べられており、憲法を変えなくてもいわば条理解釈によって政策変更も可能だということを我々も理解せねばなりません。
ただし、敵地攻撃の効果を過信している右派がいますが、弾道ミサイルも近年は移動式トレーラーに搭載するのが主流で、これでは、単に能力を持ったとしても技術面で様々な問題が出てきます。
この論文紹介の最後に、敵地攻撃能力を持つことで選択肢は増えるものの、敵地攻撃能力で達成すべき戦略的目標を明確にし、適切な組み合わせ方を模索することが重要であると論じています。
この記事で改めて敵地攻撃能力に関する知識を整理し、本質的な議論ができるよう、我々も努めなければなりません。
militarywa